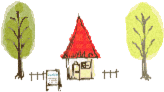[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
「太陽が丸いから、こもれ陽も丸い。もしも星型だったとしたら…、こもれ陽も星型になる」
この夏、名古屋の中心地にある名城公園で、星型の照明から降る光を「星獲り網」で捕まえるというインスタレーションがありました。ロマンを感じさせられる美しい発想ですね。
アイチトリエンナーレの一つとして取り組まれたものです。この「星のこもれ陽プロジェクト」を考えたのは、木村崇人さんという方です。以下はオフィシャルページです。
http://www.takahitokimura.com/
木村さんは、ふだんは意識していない自然の力を視覚化するような作品をいろいろに作っています。名づけて「地球と遊ぶ」というテーマです。
また、ごく最近になって読んだ本で見つけたものですが。「ゆで卵を回転させると立ち上がる」らしいのです。名づけて、「ケンブリッジの卵」です。
詳しくは、「ゆで卵を机に水平に置いて、勢いよく回転させると次第に立ち上がっていく」という現象です。
生卵を同じように回しても、立ち上がることはないんです。やってみましたが、立ち上がりません。
でも、ゆで卵ならば、「慣性の法則により、中身の液体がはじめはついてこられず、回転速度が遅くなる。だが、いったん勢いがつくと、卵を手で止めても中身は回っているので、離すと再び回り始めます」
この現象を理論的に解明された方がいます。下村裕さんです。こんなこと証明してもノーベル賞が頂けるものでもないのに、懸命に取り組む人がいるんですね。
http://web.hc.keio.ac.jp/~yutaka/
なんだか、こちらもハッピーな気分になれます。ところで、生卵の尖ったほうを下にして、立たせることができるんですが…、これじゃあ面白くないんでしょうネ。 クスン
クスン
なお、以前にこのブログでアップル社のスティーブ・ジョブさんの名言、「Stay hungry Stay foolish!」をご紹介していると思います。
この「Stay foolish」とは、愚かになれ!ということではないことは、たぶんわかっていらっしゃるだろうと思いますが…。
既成概念にとらわれずに、自由な発想で、さまざまな現象に気付くこと、また、それらで自由に遊ぶことができる、豊かな感受性を持つことでもあるんですね。
ちなみに、愛知トリエンナーレは、10月31日まで開かれています。面白い作品を見つけられると思います。
稲が十分生育してないにもかかわらず、稲刈りをすることになりました。
写真の左のほうは、「自然農法」の田んぼです。葉が黄色く色づいています。早稲の苗を植えたからです。
右のほうの田んぼは、「冬水田んぼ」という農法で、晩生の苗ですから、葉の色はまだ緑がかっています。
2つの農法にトライして比較しながらやってみましたが、自然農法のほうが実りが多そうです。しかし、「冬水田んぼ」のほうは、雑草類も多種あり、蜘蛛や昆虫、蛙なども多種です。
歩くたびに蛙が驚いて飛び跳ねるほどで、数も多いため、蛇もよく見かけます。絶滅危惧種も見かけており、さすがエコ農法です。
ちなみに、一緒に米作りをしている友人は草花や生き物たちの名をよく知っています。田んぼで作業していたと思ったら、かがんで地面見つめて、「ちょっと来てぇ!」です。
「ほらキクモよ…」と指差して説明してくれます。「ほら見て!」の連発です。その他、イボクサ、コナギ、オモダカ、アゼムシロなどもあるという。
なお、「夜は(田んぼが)イノシシのホコテンになってしまう」と気が気ではないみたいです。イノシシ避けになると思うのか、タバコの吸殻を田んぼに撒いたり、トウガラシを撒いたり…。
なんと、自分の使っていたタオルや手袋なども、臭いに敏感なイノシシ避けになると考えてか柵にぶら下げています。そんなことで効果があるとは思えないのですが…。
とまあ、そんなわけで、予定より早く稲刈りをすることになったのでした。写真・上は、刈り取った稲を「はさぎ」に架けたところです。一週間ばかり干して、晴天が続けば脱穀ができるようになるそうです。
このはさぎは、田んぼのオーナーが作っておいてくれました。また、稲の束ね方を教えてくれるご近所さんなど、周囲の人たちにいろいろなことで助けられています。
写真・下は青大将が、カエルを飲み干しているところです。ひめいのような鳴き声を聞きつけて駆けつけると、はやカエルはぐったり。1メートルはある蛇で真正面から見ると迫力があります。(写真をクリックすれば拡大されます)
ところで、刈り入れのために応援の人がひとり駆けつけてくれましたが、稲刈りは朝の9時半から6時半ころまでかかりました。途中、昼食や休憩で2時間くらいかけたかもしれません。
4人で稲を束ねてはさぎにかけるまで、約7時間にかかっています。近頃は夜になるのが早くなったので、真っ暗な中、車のライトを点けて作業を続けたのですから、今、あちこちと体が悲鳴をあげています。
来年もトライできるのかと、ちょっと後ろ向き…。
さて、この夏の思い出は暗くて苦しいものばかりだとしたら、グロリア・ゲイナーの元気の出る曲を聴いてみてはいかがでしょうか。
「I WILL SURVIVE」は、70年代にヒットした曲です。「あんたなしでも、私はちゃんとやっていけるわ」という失恋の曲ですが、逞しいエネルギーを感じられるものです。
グロリアのYOUTUBE画像→http://www.youtube.com/watch?v=Tth-8wA3PdY
歌詞
↓
At first I was afraid I was petrified.
Kept thinking I could never live without you by my side.
But then I spent so many nights
Thinking how you did me wrong. And I grew strong!
And I learned how to get along!
So now you're back from out of space.
I just walked in to find you here with that sad look upon your face.
I should have changed that stupid lock!
I should have made you leave your key!
If I had known for just one second you'd be back to bother me.
Go on now, go, walk out that door!
Just turn around now
cause you're not welcome any more.
Weren't you the one who tried to hurt (crush) me with goodbye?
Did I crumble Did I lay down and die
Oh no, not I! I will survive!
Oh and as long as I know how to love I know I stay alive.
I've got all my life to live, I've got all my love to give.
And I'll survive! I will survive! Hey, hey.
なお、26日づけで、犬のページの記事を更新したことをお知らせします。以下です。
タイトルは、「女王さまのような犬を躾ける方法」です。
http://www.mirai.ne.jp/~ryutou-m/eneagram/active/page17/memo/9.htm
女王さまのような犬は、タイプ7w8で、飼い主の男性はタイプ4w3です。「躾ける」という言葉はちょっと好きになれないものですが、なんとなく使ってしまうようです。
とくに、怒ったり、手をあげて躾ける、ということにかなり抵抗を感じます。また、犬や動物は、そのような躾け方ではうまく行きません。犬でも人間でも同じです。手荒な方法では、よい関係は築けないのではないでしょうか。
今日は、話題の動画を、3つご紹介したいと思います。なお、ここに載せているのは一つだけですが残りはそれぞれのアドレスをクリックして見て下さいね。
(なお、この動画は字幕が付いていません。でも、以下のアドレスをコピーして飛んでください。日本語の字幕が付いています→http://labaq.com/archives/51455244.html
ここの英訳が一番ベスト。面倒ですみません。字幕つきの動画を載せられないみたいです)
上記の動画は、ニック・ブーイッチさんです。オーストラリア在住で現在25歳です。ニックさんは生まれつき四肢がありません。
ニックさんの公式ページhttp://www.lifewithoutlimbs.org/
『五体不満足』という本を出している乙武洋匡さんと少し似ています。でも、ニックさんのほうは左の足に当たるところに2本の指があります。
女性に向かって、「君たちはそのままでゴージャスだ」と語りかけます。グッと来るところかもしれません。
2人目は、スティーブ・ジョブスさんです。「伝説の卒業式」と言われています。12 3という3つの動画に別れていますので、転載していません。
http://video.google.com/videoplay?docid=9132783120748987670
今年5月にiPadを発売するプレゼンでの彼の姿は記憶に新しい。しばしば新製品の発売で姿を現していますが、いつも黒のトレーナーとジィーンズです。
アップル社が赤字続きだった時、給与は毎年1ドルしか受け取っていないことは有名。むろん成功報酬などはもらっていた。が、2004年はストックオプションのほかの成功報酬はなく、本当に1ドルだけ受け取っているらしい。波乱万丈で破天荒な生き方には驚かされます。
スティーブ・ジョブズさんが語ったことで、私にとって印象的だったことは、「死は生命の最大の発明なんだよ」です。それと「Stay hungry Stay foolish」
3人目は、ランディ・パウシュの「最後の授業」と言われているものです。ガンに侵されて余命はあと数ヶ月の時に、大学でなされた授業です。既に亡くなられている方です。妻と3人の幼い息子を残して…。
公式ページ→http://www.tkd-randomhouse.co.jp/last_lecture/index.php
こちらの動画はYouTubeにもあります。でも1~9までと長いのでちよっと時間がかかるかもしれません。でも、ムダな時間にはならないでしょう。
3人の境遇の違いは大きいのですが、学べることはとても多い。全てのことは自分自身が招くことだと。自分が変われば世界は変わる、すべてのことはみな自分自身の物事の捉え方いかんなのだと語っているように思います。
1ヶ月ぶりに田んぼの草刈をしました。写真にあるように無事に実っています。えらいもんですね。ちゃんと実が生っているんですから(当たり前か…)!
ところで、1週間前にイノシシが田んぼに侵入し、稲を5.6株倒されていました。でも、近くの田んぼは侵入していないのです。この地区でイノシシ避けの柵などがある所は一つも見当たりませんからね。
どうやら、無農薬の田んぼゆえ、イノシシの餌であるミミズなどが我が田んぼには一杯にあるからではないかと。
なお、田んぼには「メダカ」と「イチョウ浮き苔(写真左)」が見つかりました。どちらも絶滅危惧種です。
メダカのほうはあまりにも小さく、また、すばやく動くので、写真に撮れなかった。残念! (ちなみに、写真をクリックすれば拡大される)
昨年の12月から水を入れて田んぼ作りを始めたばかりなのに、これまでやってきたのは、ニホンアカガエルとコオイムシ、そして、今回のメダカと浮き苔です。早くもこれだけの絶滅危惧種と出会えるんですから…。
農薬さえ使わなければ、すぐに以前のような豊かな生態系が復活するのではないかと、そんな楽観的なことさえ思い浮かびます。
ところで、メダカは海外でも"medaka"という語が使われるほど生物学界ではよく知られています。日本に棲息する最も小さな淡水魚です。
イチョウ浮苔(ウキゴケ)は、イチョウのような形の葉をしています。胞子で増えるので、農薬の影響を受けやすいものです。日本で唯一つの水面に浮遊するコケの仲間です。
写真の隣にある黄色い稲は、他の方の田んぼです。当方よりも、1ヶ月くらい前に苗を植え付けています。早くも9月半ばには稲刈りをするそうです。
一方、まだ青い穂が見えるのが、私たち(3人でやっている)の田んぼです。
こちらは一株に1つの苗を植えつけただけです。お隣りの田んぼは一株に5つくらいの苗を植えつけています。
でも、一見だけなのですが、どちらも同量くらいの実が実っているように見えます。でも、当方のほうが茎が太いんです。台風などに遭っても、太い茎が支えてくれそうで頼もしく見えます。
ところで、収穫量が同じだとしたら、苗の費用に関しては、こちらは五分の一で済んでいることになります。農協などでは一株5つかそれ以上は植えるように指導されているのだろうか??
農協に出向いたことはないので知りませんが、知り合いの自然農法の田んぼは、一株2つの苗を植えていました。
また、他の方の田んぼの中は、雑草が物凄いほど繁殖するので、ラジコンで除草剤をまいています。危うく我が田んぼまで、一緒くたに薬を撒かれてしまうところでした。
危機一髪で回避できたようですが、それは土地のオーナーが注意を払っていてくれたお陰です。
また、近くの農家の人たちから、“雑草も生えない田んぼ”とからかわれていたようです。肥料もわずかしか入れてないので雑草の繁殖も少なかったので、草刈もあまりせずに済みました。
でも、それでは米の実りも少ないと予想されるのは当然のことです。でも、見た限りでは、堂々と引けを取らないくらいに実っています。えっへんです。
約2ヶ月前に箪笥を整理している時、父の軍隊手帳を見つけました。長くかえりみることがなかったので、箪笥の奥に隠れていたものです。
手帳はボロボロですが、台風に遭って水濡れになったためだと聞いています。
終戦記念日の今日、この手帳のことを取り上げてみようと思い立ちました。でも、軍隊手帳なるものをまじまじと観察したのははじめてのことです。
最初のページに「勅諭」が印刷されていますが、なんと「勅諭」が3つもあります。1つ目は、明治15年1月4日の日付になっています。調べてみると、その日に、「陸海軍に軍人勅諭を発布」がされたみたいです。
参謀本部長の山県有朋が西周(にしあまね)に起草させたものだそうです。その当時のことを描いた画を転載しています。また、以下に勅諭の全文が載っています。
http://www.asahi-net.or.jp/~uu3s-situ/00/Gunzin.tyokuyu.html
2つ目は、大正元年7月31日付けの勅諭です。明治天皇が30日に崩御して、大正に改元した日です。3つ目は、昭和元年12月28日づけの勅諭です。大正天皇が25日に崩御して、昭和に改元した日です。
つまり、明治・大正・昭和の3代の天皇がそれぞれに勅諭を出しています。しかも、この3つの勅諭は赤字で印刷されています。赤紙ってわけです。これ以外はみな黒字で印刷されています。
勅諭の次に載っていたのは、「勅語」です。ちなみに、勅諭は勅語より訓示的なものなんだそうです。大正3年11月3日下賜とあります。
その後にも全部で8項目あって、本人が署名や記入するようになっています。ですから、父の直筆の署名が見えます。よく見知っています。懐かしいなつかしい字です。
表紙の布は麻らしく、紙は丈夫な薄い和紙で作られています。水濡れに遭っても、印刷された字は読めます。
父の軍隊手帳には載っていませんでしたが、教育勅語と戦陣訓が載っているものもあると聞いています。父より歳若い兵士たちの手帳にあるそうです。
この戦陣訓には、「生きて虜囚(りょしゅう)の辱めをうけず」というものがあります。沖縄で集団自決したり、女学生たちが自害した、その大元になる訓示です。
ところで、父が最初に配属されたのは、「第三師団」で、 部隊は「輜重兵第三大隊第一中隊」で、二等兵でした。
ちなみに、師団とは6千人から2万人程度の兵員規模の作戦基本部隊のことです。これも調べてみてはじめて知ったことなんですが。
そして、輜重兵(しちょうへい)とは、兵站(へいたん)と言って、主に陸軍の後方支援をすることで、兵器や燃料や食糧を輸送や補給したり、兵器の修理なども行う兵科のことです。
兵役には付きましたが、父はそのころ病弱で結核を患ったので、国内での「農耕勤務隊」に転属されました。外国で敵と対峙して人を殺すというような体験はしていないようです。
でも、内地で農耕作業に携わるのは屈辱的なことだったみたいです。お国のために戦えない兵士では、周囲からの風当たりが強く、辛い思いをしたのではと思います。
結核を患っても病院に入院できるものではなく、きつい農作業だったみたいです。父は寡黙なので、そういう話をしたところは見たことも 聞いたこともありません。他の体験者が教えてくれたことです。
また、この手帳を見ると、そこには農耕作業に従事していた、と、はっきりと書かれていました。こうして、手帳を写真に撮って、細かく調べていくと、まざまざと、なんだか幻影のようなものが見えてくるような感じです。
父はどんな思いで、この手帳とつきあい署名したのだろうか。勅諭は暗記したのだろうか。何も語らないままに逝ってしまったので、もう尋ねることも、確かめることもできません。
最近まで軍隊手帳のことをかえりみることもなかったので、申し訳ない気持ちで一杯になります。これを書きまとめて、やっと少し気持ちが収まってきましたが…。
今年に入って、二人の知り合いが亡くなったという知らせを受けています。同年輩の方の死は、わが身に迫るものがあります。私に残された時間は後どれくらいだろう、などと考えたりしてしまう。
また、古い友人に電話をすると、家族が電話口に出て、入院していると告げられる。ガンかもしれないと言う。すると、健康診断に行ったのはもう12年前だなあと気づく。
また、今年は若い頃から親しんで著書を読んでいた方々の死亡記事を見つけており、こちらもショックな知らせです。井上ひさし様・多田富雄様・梅棹忠雄様・森毅様。改めてご冥福をお祈りします。
なお、ウィキペディアに載っていたのですが、井上ひさしさんは、毛筆で書くことを人に頼まれた場合に、よく書いた文章があるそうです。それは…、
「むずかしいことをやさしく/やさしいことをふかく/ふかいことをゆかいに/ゆかいなことをまじめに書くこと」 なんと、私が手帳に書きとめていたことです。
また、多田富雄さんの著書、『免疫の意味論』にはかなり驚かされました。免疫現象の意味を考えていくと、生命観そのものまで変わってしまう感じです。
梅棹忠雄さんを知ったのは、『知的生産の技術』(岩波)からです。本棚に今もあります。そして、ウィキペディアではじめて知ったのですが、井上ひさしさんと梅棹忠雄さんはともにエスペランティストだったんですね。私もしゃべられない自称エスペランティストです。世の流れにムダに抗っています。
森毅さんの本は、語り口が面白くて読んでいたように思います。たくさんの著書がありますが、ちくま文庫の『いいかげんが面白い』がおすすめです。
ウッキペディアで調べたら、死亡記事が出た当日に、早くもそれぞれの箇所が書き換えられています。これも、なんだかショックなことです。 元気の出る本知っていたら、お知らせください。
ロシアとか欧州などの山火事がすごいことになっています。その映像を以下のところでご覧ください。クリックすれば飛べます。
http://englishrussia.com/index.php/2010/07/31/the-moscow-region-on-fire/
上の画面は、ロシアの山火事の発生件数を示しています。その範囲は広大で、これほどまでだとは…。(画像も、クリックすれば拡大されます)
たぶん予想以上なはずです。それで、ご紹介したいと思いました。昨日の7日も、首都モスクワが森林火災で発生したスモッグに包まれたと報道されています。
「クレムリンの大聖堂などの観光名所も分厚いスモッグでかすんで見え、自動車は昼間からヘッドライトをつけて走っている。大気中の一酸化炭素濃度は公衆衛生上の最大許容値の5倍に達した」
「またロシア非常事態省によれば、過去24時間で244か所の火災が鎮火した一方、新たに290か所で火災が発生し、火災発生件数が鎮火件数を上回っている」AFP
日本は湿度の高い国だからなのか、山火事はそれほど多くないが、こちらは元々空気が乾燥しているからなのであろうか。
ロシア政府は小麦の国外輸出禁止を決めたそうですが、これをみたら納得できるのではないでしょうか。今年の異常気象は普通じゃありません。
う? ちょっとおかしいかな。普通じゃないから異常気象って言っているんですよね! でも、異常気象が続いていると、こんな言葉使いも有り! かも…
これからどうなるんだろう。もっと酷くなりそう…などと想像すると恐怖で震えてきます。それでも、このような山火事は生まれて始めて知ったものです。
台風の怖さはよく知っているのですが…。床上浸水で、しかも、天井まで届きそうな水位でしたから…。
暑中お見舞い申し上げます。
暑さに弱いので、今年の夏季休暇は高い山に行けば涼しいだろうと思って、とある高地に行きました。が、なんと、そこも有り得ない猛暑でした。
避暑に行ったつもりなのに、暑い日中、歩き回って夏バテしてしまい、おまけに夏カゼにもかかってしまいました。みなさんは、どのようにしてこの暑さを凌いでおられるのでしょうか…。
ところで、前回は、「不安に絡め取られない方法」というタイトルの文を載せています。大人や年寄りよりも、若者たちのほうが不安に陥りやすい傾向はあるかもしれませんが、実は何歳になっても不安というものは訪れます。
歳を取るほど死が近づくのですから、そんな死の恐怖もあり、病気や孤独感も、若者より深刻です。また、友人や知り合いたちが次々に逝ってしまうのですから。
生きている限り、不安というものから逃れることはできません。私にもよく起きます。でも、そんな時にやってみることがあります。それは…、
夜空を眺めることです。また、宇宙とか銀河系とか、原子核とかクォークなどに関する本とか写真を眺めたりします。すると気分が変わります。なんて小さなバカバカしいことに悩んでいたのだろう、とハッと気づかされるのです。
今回は、レイ&チャールズ・イームズの「パワーズ・オブ・テン」という有名な動画をご紹介したいと思います。20世紀映画界の最高傑作の一つだと言われているのだそうです。
http://www.youtube.com/watch?v=0fKBhvDjuy0&feature=BF&list=PL879CA4197E6D2E59&index=44
(ちなみに、見られない場合は、上記のほうで観てくださいね)
最初のシーンは若いカップルが芝生に寝転んでいて、暖かくて幸福そうです。そして、そこからズンズンとズームアウトして、太陽系から銀河団にまで到達します。
大銀河団や世界の淵まで行って欲しいのですが、ちょっと無理なんでしょう。でも、場面は一転して、遺伝子、原子、素粒子というミクロの世界にまで行きます。
でも、素粒子の世界など見た人などいないのですから、想像して作られた画面ですから、誤解しないでくださいね。
こういう動画を見ると、私たち人間が、狭い狭い極小の世界に閉じ込められていることを思い知らされます。蟻や蚊やウイルスたちとなんら変わらない存在なんだと…。
というよりも、ちょっとだけ思考できる卑屈な極小生物なんだなあ、と思い返すことができるのです…。視野とか視点というものをちょっと変えるだけで、不安という檻から抜け出せるように思われます。
でもってですね。今週は冷房の効いた科学館に行ったり、プラネタリウムに行ったり、夜は星空を眺めて見ませんか?
「不安」というものは恐ろしいもので、一度それに絡め取られてしまうと、そこか抜け出すのは容易ではありません。不安感が強くなると、どんなことでも不安の種になってしまうのです。
今回は、「不安」とどうつきあったらいいのか、それに絡め取られないためには、今何をしたらいいのかを、少しまとめてみました。なにかで役立つことがあればと願っています。5つの項目にまとめています。
①不安が高まると苦しくなって、そこから逃れることを考え出しますが、かえって不安に絡め取られてしまうだけです。専門医のところに行って相談しても、大抵は安定剤などの薬を処方してくれるだけに終わります。
薬を飲んでもただ眠くなるか、頭をもうろうとさせるだけで、薬が切れたら、それ以前より不安感が強くなる怖れがあります。また、その時間ムダに過ごしたことで、また自責の念にとらわれて、ますます焦りだします。
誰も自分を助けてくれないと感じて、絶望感と孤立感で一杯になります。頼れる人に相談しても、カウンセリングを受けても、、一時しのぎに過ぎず、不安感は少しも減らなかった、という体験ならば、たぶん、多くの人たちがしています。
②面白いサイトを見つけています。神経症を無くすために次ぎのことを全て実行してはならないと言うのです。たとえば、薬などの安定剤 森田療法、催眠療法、自律訓練療法、行動療法、心理分析、感謝、懺悔、断食、苦行、逃避、座禅、深呼吸、瞑想等
その通りだと思います。エニアグラムの性格分析もしないほうがよいと考えます。また、そんな自分の精神状態を書き出してみようと日記につけたり、友だちに手紙を書くのもやめたほうがよいでしょう。家族に悩みを訴えたり、愚痴などもこぼさないほうがよいと考えています。不安が不安を招くようになるからです。
③さて、こちらからの提案は、頭が心配事に占拠されているので、頭は使わないで身体をしっかりと使いましょう、というものです。つまり、懸案の問題を片付けるよりは、すぐに気軽にトライできることからやろう、というアドバイスなのです。
不安感が嵩じると、交感神経の興奮状態が続きますから、夜になっても寝付けず、生活のリズムが乱れてきて、自律神経のバランスがくずれます。そうなると余計に不安感が増します。
そうならないためには、昼間は体をしっかりと動かして、夜には副交感神経がよく働くようにさせねばなりません。つまり、昼間運動すれば、夜は熟睡できるようになります。どちらの神経もしっかりと働かせることができれば、心身の健康を取り戻せると考えられるからです。
④まずは朝晩2回、15分くらいヨガとかストレッチなどにトライされることをお勧めします。さらに、勤務されているならば、通勤時や昼の休憩時を活用して、歩いたり、スロージョギングなどをしてください。1ヶ月続けたら、それだけでも不安感が減ります。
休日には、できるだけ野山を歩き回ってください。街中でショッピングしたり、映画を観たり、友だちとおしゃべりしても、帰宅すれば不安感が舞い戻ってきます。しかし、自然の中で体を動かすと、気持ちが全く違ってきます。不安が小さく萎んでいると発見できることがあります。
⑤自宅にいても、テレビを見ないで、ラジオならば聴きながらでもいいのですが、掃除したり、洗濯や料理などで体を動かしてください。少し気分が回復したらトライしてください。
あまり回復していないのであれば、夏ならば郊外にでかけて森の中でキャンプしてください。冬であれば雪遊びなど、親しい人としてください。その他、テニスや卓球などの教室に通うのもいいものです。
以上のようなことを、夏休みを取って、気分転換を図ってください。なにがしかの運動をして汗を流すと、自分の心が健やかになっていると気づくと思います。
出来る限り、郊外や海山に出かけてみてください。自然が癒してくれるかもしれません。また、あなたの中に元からある自然治癒力も高まってきます。
なお、人ごみの多いところはできるだけ避けてください。気を使わなくて済む安心できる人と2、3人で、ゆったりとした休日を過ごすのがベストです。
| 01 | 2026/02 | 03 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |